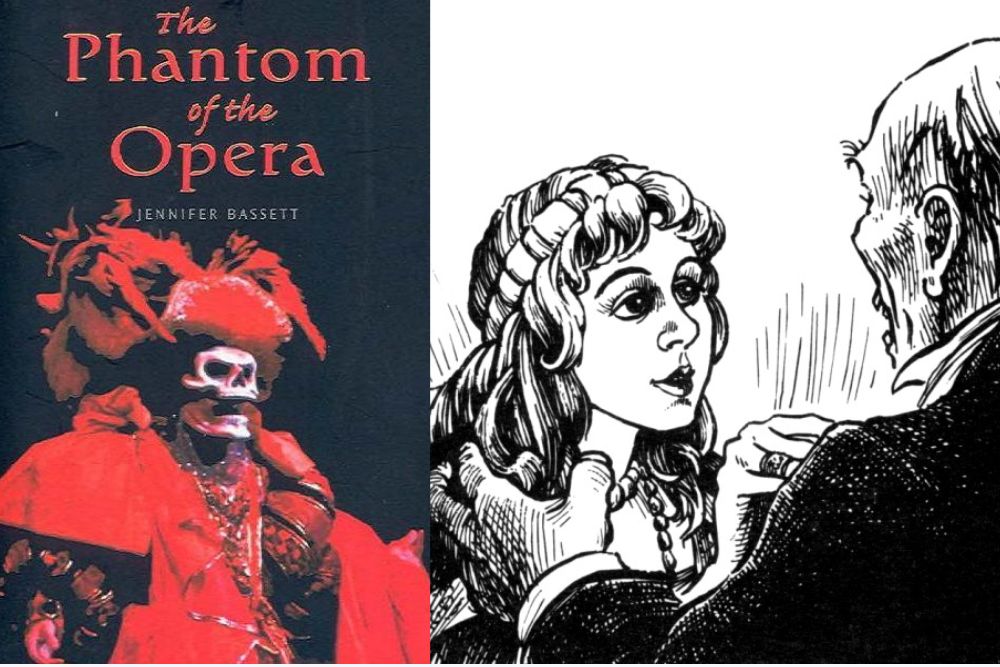(背景情報:パリの壮麗で迷宮のようなオペラ座を舞台に、『オペラ座の怪人』は若きソプラノ歌手クリスティーヌ・ダーエの物語を描きます。彼女が突然花開いた歌の才能の裏には、「音楽の天使」と呼ぶ謎の教師の存在がありました。その正体は、恐ろしい容貌を持つものの、建築や音楽に卓越した才能を持つ男――すなわちオペラ座の地下に潜む「怪人」エリックだったのです。
しかし、クリスティーヌが幼なじみの恋人ラウル・ド・シャニーと再び愛し合うようになると、怪人の執着は狂気へと変わり、ついには彼女をさらう事態へと発展します。ラウルの命を救うため、クリスティーヌは「怪人と結婚するか、愛する人が拷問にかけられて死ぬのを見届けるか」という、絶望的な選択を迫られるのでした。)
※ 注記:本作の原典はガストン・ルルーによる1910年の小説『オペラ座の怪人』ですが、ここで紹介する物語はジェニファー・バセットによる簡約版をもとにしています。複雑な筋を整理しつつ、拒絶が生む苦しみ、そしてそれを打ち破る慈悲の力という物語の核心を描き出したため、この版を選びました。物語をより深く味わいたい方は、ぜひルルーの原作小説にも触れてみてください。
パリのオペラ座は世界でもっとも有名で、美しい建物です。世界最大規模を誇るその劇場の地下には、陽の光を一切見ずに何時間でも歩き続けられるほどの広大な迷宮が広がっています。
そしてそのオペラ座には、幽霊が棲んでいるのです。
黒い衣をまとった怪人――。
頭のない身体なのか、それとも身体のない頭なのか。黄色い顔に鼻はなく、眼窩は真っ黒な穴となって空いている……。
これは、オペラ座の怪人の物語です。
第1部:オペラ座の支配人たち
その週は、オペラ座にとって新しい始まりの週だった。二人の新しい支配人――アルマン・モンシャルマン氏とフィルマン・リシャール氏――が着任したのだ。
「アルマン、この手紙をどうするつもりだ?」
机の上に置かれた手紙を見つめながら、フィルマンが言った。
「どうするって? 何もしないさ!」アルマンは声を荒げた。「どうしようもないだろう!」
二人はもう一度その手紙を読み返した。短いものだったが、内容は奇妙だった。
――新しい支配人へ
あなた方がオペラ座に来たばかりなので、いくつか大事なことを伝えます。
オペラの夜には決して5番ボックスのチケットを売ってはなりません。そこは私の席です。ドア係のジリー夫人が事情を知っています。
それから、私はオペラ座での仕事のために資金を必要としています。私は多くを望みません。ひと月わずか二万フランで満足です。
以上です。お忘れなきように。私は良き友にもなれますが、悪しき敵にもなり得ます。
O.G.
「5番ボックスを売るな? 二万フランだと!」アルマンは怒りに震えた。「あそこは劇場で一番の席だぞ! 我々には金が必要なんだ、フィルマン! それに、このO.G.って誰のことだ?」
「Opera Ghost――オペラ座の幽霊に決まってるじゃないか」とフィルマンは肩をすくめた。「だが君の言う通り、どうしようもない。くだらない悪ふざけさ。我々が新参だから愚弄しているのだろう。オペラ座に幽霊なんているはずがないさ!」
二人は話題をその夜の公演へと移した。演目はグノーの『ファウスト』。本来ならマルガリータ役はラ・カリオッタが歌うはずだった。彼女はスペイン出身で、パリ随一の歌姫である。
ところが、そのカリオッタが突然病に倒れたのだ。
「今夜はパリ中の人々が劇場に集まるというのに……」アルマンが苛立たしげに言った。「なのに今朝になって急に【病気で歌えません】だと! 手紙一本で済ませるとは!」
「落ち着け、アルマン。代役ならいる。ノルウェー出身の若い歌手、クリスティーヌ・ダーエだ。彼女にマルガリータを歌わせよう。声はいい」
「だが彼女は無名だし、若すぎる! 客は誰も新人など聴きたがらん」
「いや、もしかしたらカリオッタより上手いかもしれん。誰にも分からんさ」
第2部:リスティーヌ・ダーエ
フィルマンの予想は正しかった。
その夜、グノーの《ファウスト》でマルガリータを演じた新人歌手――クリスティーヌ・ダーエ――の歌声に、パリ中が熱狂したのだ。天使のように澄み渡る声、美しく伸びやかな響き。観客は笑い、涙を流し、そして喝采を惜しまなかった。
「ダーエこそ世界一の歌手だ!」
劇場は歓声で満ち、彼女は一躍、時の人となった。
舞台裏で、バレエの少女メグ・ジリーは、踊り子仲間のアニー・ソレリに小声で話しかけた。
「クリスティーヌ、あんなふうに歌ったこと、今まで一度もなかったわ。どうして今夜はあんなにすごかったの?」
「新しい音楽の先生でもついたんじゃない?」アニーが答えた。
一方、14号ボックス席では、シャニー家の長兄フィリップ伯爵が、弟に向かって微笑んでいた。
「どうだ、ラウル? 今夜のダーエ嬢の歌は?」
ラウル・ド・シャニー子爵は二十一歳。青い瞳に黒髪、そして誰をも惹きつける優しい笑顔を持つ青年だった。シャニー家は古くから続く名門の大貴族で、裕福でもあったから、パリの多くの娘たちが若き子爵に心を寄せていた。
だが、ラウルの心には他の誰も入り込む余地がなかった。
兄に微笑み返し、ラウルは言った。
「何と言えばいいのか……クリスティーヌは天使だよ。それだけだ。今夜は必ず彼女の楽屋に行くつもりだ」
二十歳年上のフィリップは、父親のような視線で弟を見つめ、愉快そうに笑った。
「なるほど……恋をしているな! だがラウル、今夜がパリでの初日だろう? オペラ座に来るのも初めてじゃないか。どうしてクリスティーヌ・ダーエを知っているんだ?」
「覚えているかい? 四年前、僕がブルターニュの海辺で休暇を過ごしていた時のことを。あの時、彼女と出会ったんだ。あの頃からずっと、僕は彼女に恋をしている。そして今も変わらない」
「ふむ……そうか」伯爵はゆっくりと頷いた。「だがラウル、気をつけるんだ。彼女はただの歌手にすぎん。我々は彼女の家柄も何も知らない」
しかしラウルは兄の忠告を耳に入れなかった。彼にとって、家柄などどうでもよかったし、若者というものは年長者の言葉に耳を貸さぬものなのだ。
その夜のクリスティーヌの楽屋は、多くの人で賑わっていた。だが彼女の傍らには医師がつきそい、その顔は青ざめ、病人のように見えた。
ラウルは人混みをかき分けて駆け寄り、彼女の手を握った。
「クリスティーヌ! どうしたんだい? 具合が悪いのか?」
彼は椅子に座る彼女のそばにひざまずいた。
「覚えていないかい? ブルターニュで出会ったラウル・ド・シャニーだ!」
クリスティーヌは怯えたように青い瞳を向け、そっと彼の手を振り払った。
「……知りません。お願い、出て行ってください。私は……具合が悪いんです」
ラウルの頬はみるみる赤くなった。言葉を発する前に、医師が早口に言った。
「はいはい、もうお帰りください! 皆さん、ここから出てください。マドモワゼル・ダーエには静養が必要です。ひどく疲れているのです」
彼はすぐに扉の方へ誘導し、やがて楽屋には誰も残らなかった。クリスティーヌは一人きりになった。
廊下に出た若き子爵の胸には、怒りと失望が渦巻いていた。
――どうして彼女が僕を忘れるものか? どうしてあんなことを……?
ラウルはしばらく待ち、静かに、慎重に彼女の楽屋の扉へ戻ってきた。開けようとしたその時、室内から男の声が聞こえた。
「クリスティーヌ、君は僕を愛さなければならない!」

ジェニファー・バセットによる『オペラ座の怪人』
次いで、クリスティーヌの声が応えた。
「そんなことを言わないで……。私はあなたのためだけに歌っているのに。今夜、私はすべてをあなたに捧げたのよ。私はもう、とても疲れているの……」
その声は怯えと悲しみに満ちていた。
「君は天使のように歌っていた」
再び男の声が響いた。
ラウルは愕然とし、静かにその場を離れた。
――そうか……クリスティーヌには恋人がいたのか。
だがなぜ彼女の声はあんなにも悲しげなのか?
ラウルは廊下の影に身を潜め、待ち続けた。敵とも言うべき「彼女の恋人」の姿を、この目で確かめようとしたのだ。
やがて、十分ほどしてクリスティーヌが楽屋から出てきた。彼女は一人きりで、静かに廊下を歩き去っていった。
しかし、後から男が現れる気配はなかった。廊下には誰の姿もない。
ラウルは決意を固め、素早く楽屋の扉へ向かうと、勢いよく開けて中へ入った。扉を閉め、声を張り上げた。
「どこにいるんだ! お前がここにいるのは分かっている! 出てこい!」
……だが返事はなかった。
ラウルは部屋中を探し回った。椅子の下、衣装の陰、暗い隅々まで――。
しかし、そこには誰の姿もなかった。
第3部:怪人の怒り
水曜日の朝、アルマンとフィルマンの二人の支配人は上機嫌だった。
新人歌手クリスティーヌ・ダーエのマルガリータ役は大成功を収め、パリ中がその歌声を絶賛していたからだ。何もかも順調で、人生は輝いて見えた。
次の公演は金曜日、演目は再び《ファウスト》。だが今度はラ・カリオッタがマルガリータを歌う予定であった。
ところが、水曜の午後にはもう二人の顔は曇っていた。新たな手紙が届いたのだ。差出人は――O.G.。
――なぜ私の言うことを聞かないのか。私は怒っている。
5番ボックスは私の席だ、必ず空けておけ。
そして、私の二万フランはどこにある?
金曜日の夜はダーエにマルガリータを歌わせろ。彼女こそ今やパリで一番の歌手だ。
カリオッタには歌わせるな。あの女の声は醜い、まるでヒキガエルの鳴き声だ。
忘れるな。私は良き友にもなれるが、悪しき敵にもなる。
――O.G.
「これでもまだ冗談だと思うのか、フィルマン!」
アルマンは顔を真っ赤にして叫んだ。「我々が支配人なのか? それともO.G.が支配人なのか?」
「まあまあ、アルマン、落ち着け」フィルマンは疲れた声で答えた。「私にも分からん。だがジリー夫人に聞いてみよう。5番ボックスのドア番だし、何か知っているかもしれん」
こうして二人はジリー夫人を呼んだ。だが彼女は、幽霊も支配人も恐れぬ女であった。
「ジリー夫人、あなたはオペラ座の幽霊の友人だと聞きますが」とアルマンが切り出した。「あの幽霊について教えてください。人によっては【頭がない】と言い……」
「いや、身体がないと言う者もいる」とフィルマンが続けた。「あなたはどう思うのです?」
ジリー夫人は二人をじっと見つめると、ふっと笑い声をあげた。
「私が思うに、オペラ座の支配人は愚か者だ、ということです!」
「な、なんだと!」アルマンは激昂し、椅子から立ち上がった。「いいか、女――」
「まあ座りなさい、アルマン。まずは話を聞こうじゃないか」フィルマンがなだめた。「なぜそう言うのです、ジリー夫人?」
ジリー夫人は静かに言った。
「お二人が幽霊を怒らせたからです。幽霊が望むものは、必ず与えねばなりません。あの方は賢く、そして恐ろしいのです。以前の支配人たちも、最初は逆らおうとしました。でもその時、オペラ座では数々の事故が起きたのです。不思議で、恐ろしい事故が……。いつ起きたと思います? 幽霊が怒っている時ですよ! だから前の支配人たちはすぐに悟りました。幽霊が5番ボックスを望めば、毎晩そこを譲る。幽霊が金を望めば、即座に渡す。そうして初めて、平穏が保たれるのです」
「だが我々こそ支配人だ! オペラ座の幽霊ではない!」アルマンは再び声を荒げ、フィルマンを振り返った。「この女は気が狂っている! なぜ耳を貸す? いいか、金曜の夜はカリオッタにマルガリータを歌わせる。そして我々は5番ボックスから舞台を観劇するのだ!」
「……まあ、試してみるのもいいだろう、アルマン。ただし、事故が起きなければいいがな」
ジリー夫人は二人に歩み寄り、低く囁いた。
「よく聞きなさい。幽霊は良き友にもなりますが、恐ろしい敵にもなるのです」
二人は顔を見合わせ、息をのんだ。
「その言葉……」フィルマンがゆっくりと口にした。「なぜそれを言うのです、ジリー夫人?」
「幽霊ご自身が、私にそうおっしゃるのです」ジリー夫人は静かに答えた。「姿を見たことはありません。でも、あの方の声はしばしば聞きます。とても美しい声でね……人に怒鳴ることもありません」
第4部:ラウルへの手紙
その水曜日、若きシャニイ子爵ラウルのもとに一通の手紙が届いた。封を切り、署名を目にした彼は微笑んだ。
――親愛なるラウルへ
もちろん、あなたのことを覚えています。どうして忘れられるでしょう?
木曜日の午後三時、チュイルリー公園で会いましょう。怒らないでね、ラウル。お願いです。
クリスティーヌ・ダーエ
ラウルは手紙を大切にポケットへしまった。怒る? 天使に向かってどうして怒れるだろうか。
木曜日、彼は二時にはもう公園にいた。三時十分、胸に不安が広がり始め、三時半には生きる望みを失うほど落ち込み、誰かを殺してしまいたいほどの絶望に沈んでいた。
だがその時、彼女が現れた。クリスティーヌが園内を駆け抜け、瞬く間にラウルの腕の中へ飛び込んできたのだ。
「クリスティーヌ……クリスティーヌ!」
ラウルは何度もその名を呼び、彼女を抱きしめた。
二人は園内を歩きながら、四年前、ブルターニュの海辺で過ごした幸せな日々を懐かしく語り合った。
「でも、なぜあの時去ってしまったの? なぜ手紙をくれなかったの?」
ラウルの問いに、クリスティーヌはしばらく黙っていた。やがて、ゆっくりと口を開いた。
「私たちはあまりに若かったの。私はただのノルウェーの貧しい歌手の娘、あなたは由緒あるシャニイ家の子爵……。あなたの妻になるなんて、夢にも思えなかったわ」
「でも僕は君を愛している!」
「いいえ、ラウル、聞いて。父が亡くなって、私はひどく悲しかった。でもパリに戻り、必死に歌を学んだの。オペラ歌手になるために。ただの歌手じゃなく、パリで一番の歌姫になるために」
「そして、今や君はその通りになった。パリ中が君にひれ伏している」
ラウルは微笑んだ。
しかしクリスティーヌは顔を背け、言葉を返さなかった。
「クリスティーヌ……火曜日の夜、君の楽屋にいた男は誰だ?」
ラウルが静かに問いかけると、彼女は立ち止まり、顔色を失った。
「男? 誰もいなかったわ」
「僕は聞いたんだ。扉の外で、男の声を。あれは誰だ?」
「聞かないでラウル! たしかに声はあった。でも部屋には誰もいなかったの。本当よ! ああ、私は怖いの……時々、死にたいほどに」
「一体誰なんだ? 僕に話してくれ。友達として助けたい。名前を教えて!」
「名前は言えないわ。秘密なの。私は彼を見たことがない。ただ声だけを聞くの。でも彼はどこにでもいる。全てを見て、全てを聞いている。だから火曜日、あなたに話せなかったの。彼は私の音楽の師なの。素晴らしい歌手で、私があんなに美しく歌えたのも彼のおかげ。私が名声を得られたのも彼のおかげなの。彼は【音楽の天使】……そう名乗っているわ。そして、彼は私を愛していると言うの。……私はどうすればいいの?」
第5部:ラ・カルロッタのマルガリータ
金曜日の朝、ラ・カルロッタはベッドの上で朝食をとりながら手紙を読んでいた。その中の一通には署名がなかった。短い文面である。
――あなたは病気です。今夜マルガリータを歌ってはいけません。家にいなさい。オペラ座に来てはなりません。事故は起こるものです。永遠に声を失いたくないのなら。
カルロッタは怒りで跳ね起き、コーヒーを飲み干すこともなく部屋を飛び出した。
「これはクリスティーヌ・ダーエの仲間の仕業に違いない。あの娘にまた歌わせたいのね。でもそうはさせない。パリ一の歌手はこの私、ラ・カルロッタよ。今夜、必ずマルガリータを歌ってみせる!」
その夜七時、アルマン氏とフィルマン氏は堂々と第五番ボックス席に入り、腰を下ろした。彼らは幽霊など恐れていなかった。
最初の一時間、カルロッタは舞台に登場せず、何事も起こらなかった。奇妙な声も聞こえず、二人の心は次第に落ち着いていった。
だがついにカルロッタが舞台に現れると、フィルマンは小声で言った。
「今、声が聞こえなかったか?」
「いや、何も……」アルマンは答えながらも、背後を二度、三度と振り返り、急に寒気を覚えた。
カルロッタは堂々と歌い始めた。何も起こらない……と思ったその時。彼女が甘美な恋の歌を口にした瞬間――
「我が愛ははじ……コ、コーアッ!」
客席全体が凍りついた。カエルの鳴き声のような奇怪な音!
カルロッタは立て直し、再び歌う。
「我が愛ははじ……コーアッ! わたしは忘れられな……コーアッ!」
人々は笑い出し、ざわめきが広がった。フィルマンは頭を抱えた。だがその時、アルマンが彼の腕を掴む。ボックス席の中に声が響いたのだ。低く不気味な笑い声だった。
必死のカルロッタは何度も歌い直す。
「わたしは忘れられな……コーアッ!」
笑い声が再び響き、今度はあらゆる方向から聞こえた。
――「今夜の彼女の歌は、シャンデリアを落とすぞ!」
二人は恐怖に顔を見合わせ、天井を仰いだ。
次の瞬間、千もの灯りを輝かせていた巨大なシャンデリアが轟音とともに吊り縄を断ち切り、観客席に落下したのである。
その夜は、パリ・オペラ座にとって悪夢の夜となった。シャンデリアの直撃で女性が一人死亡、多くの人々が重傷を負った。オペラ座は二週間の閉館を余儀なくされ、そして……ラ・カルロッタが舞台に立つことは二度となかった。

ジェニファー・バセットによる『オペラ座の怪人』
第6部:音楽の天使
その後の一週間、ラウルは毎日クリスティーヌと会った。ある日は彼女は物静かで沈んだ顔をしており、またある日は楽しげに笑い、歌まで口ずさんだ。しかし彼女は決してオペラ座のことや、自分の歌のこと、あるいはラウルの愛について語ろうとはしなかった。ラウルは彼女を案じていた。――一体誰なのか? この奇妙な教師、「音楽の天使」と呼ばれる声の主とは。
ところがある日、クリスティーヌの姿が忽然と消えた。家にもいない、オペラ座にもいない、約束していた場所にも現れない。ラウルはあちこちを探し回ったが、誰も彼女の行方を知らなかった。
オペラ座の再開を二日後に控えた頃、ラウルのもとに手紙が届いた。差出人はクリスティーヌである。
――一時間後、オペラ座の屋上、十階で会ってください。
……
暗い片隅に腰を下ろした二人。ラウルは彼女の手を取った。クリスティーヌの顔は青ざめ、疲れ切っていた。
「聞いて、ラウル」彼女は小さく言った。「すべてを話すわ。でもこれが最後の逢瀬よ。もう二度と会えない」
「そんなことはない、クリスティーヌ!」ラウルは叫んだ。「僕は君を愛している。だから――」
「しっ! 静かに!」クリスティーヌが制した。「彼に聞かれるかもしれない。オペラ座の中では、彼はどこにでもいるのよ!」
「彼? 誰のことだ?」
「音楽の天使よ。先週の土曜に会えなかったのは、彼が私を連れて行ったから。楽屋にいたら突然、彼が現れたの。黒い夜会服をまとい、顔には仮面をつけていた……。彼は秘密の扉を次々と開き、私を導いたの。何重もの通路を抜け、どんどん地下深くへ。そこには湖があったわ。冷たく黒い水の湖。その湖を小舟で渡り、その先にある家へ……。彼はその家に住んでいるの、ラウル。オペラ座の真下、湖のほとりに」
「本当なの、ラウル! そして彼こそが――オペラ座の怪人。幽霊でも天使でもない、人間よ! 名前はエリック。彼は私を愛していて、妻にしたいと……」
クリスティーヌは言葉を詰まらせ、そして続けた。
「彼は言ったの。女は誰一人、自分を愛さないと。理由はこの顔……。そう言って仮面を外したの。私は見てしまったわ」
涙がこぼれ、ラウルは彼女を抱きしめた。
「ラウル、あの顔は恐ろしいの! 生きながら死んでいる人のよう。鼻はなく、黄色い顔には黒い穴が二つ。そして目……時には真っ黒な穴のようで、また時には不気味な赤い光を放つの!」
彼女は両手で顔を覆った。
「私は彼の家に五日間いた。彼は優しくしてくれたし、可哀そうにも思った。でも彼は私の愛を求め、私は……私は……」
「いいや、クリスティーヌ!」ラウルが叫んだ。「君は僕の妻になるんだ! 今すぐ一緒に行こう。あんな男のもとへは戻らなくていい!」
「でも戻らなければならないの」クリスティーヌは小声で答えた。「彼はあなたのことを知っている。私たちのことも。彼はあなたを殺すと言ったわ。だから……」
「そんなことはさせない! 僕は君を愛している。そして必ずエリックを倒してみせる!」
エリック……エリック……エリック……。
その名が、オペラ座の闇に囁くように響いた。ラウルとクリスティーヌは顔を見合わせた。
「い、今のは何だ? 彼の声なのか? どこから……?」ラウルは震えた。
「怖いわ、ラウル……。私は土曜日にまたマルガリータを歌うの。いったい何が起こるの……?」
「こうしよう」ラウルはきっぱりと言った。「土曜の夜、オペラが終わったら、君と僕は一緒にここを出る。そして結婚するんだ」
二人は暗い廊下をそっと進み、階段へ向かった。だが突然、目の前に男が立ちはだかった。長い黒い外套に黒い帽子の、大柄な男。彼は振り向き、二人を見据えた。
「その階段ではいけません。正面の階段を使いなさい。早く!」
クリスティーヌはすぐに駆け出し、ラウルも後を追った。
「今の男は誰だ?」ラウルが尋ねる。
「ペルシャ人よ」クリスティーヌは答えた。
「ペルシャ人? なぜ僕らを助けた?」
「誰も本名を知らない。ただ【ペルシャ人】と呼ばれているわ。いつもオペラ座にいるの。たぶん彼はエリックのことを知っている。でも口には出さない。さっきは、階段にエリックがいるのを見て、私たちを助けてくれたのかも」
二人は手を取り合い、幾重もの通路と階段を抜けて小さな裏口にたどり着いた。
「じゃあ、土曜の夜だ。オペラの後で、君を連れ出して結婚する」
ラウルは真剣な眼差しで言った。
クリスティーヌは彼を見上げて、静かにうなずいた。
「ええ、ラウル」
第7部:クリスティーヌ・ダーエはどこに?
土曜の朝、シャニュ伯爵フィリップは朝食の席で弟を見つめた。
「やめておけ、ラウル。頼む。幽霊だの怪人だの……そんな話は馬鹿げている。あの娘は気が触れているんじゃないか」
「彼女は正気だ。それに、僕は必ず彼女と結婚する」ラウルはきっぱりと言った。
「だが、彼女は所詮オペラ歌手にすぎない。しかもまだ若い。十年後、二十年後も本当に愛し続けられるのか?」
フィリップは心配そうに言ったが、ラウルは黙ってコーヒーを飲み、答えようとはしなかった。
その夜の幕開けは華やかだった。オペラ座にはパリ中の人々が集まった。誰もが再びクリスティーヌ・ダーエの歌声を聞きたかったのだ。それに、彼女とシャニュ子爵ラウルの恋の噂も、すでに広まっていた。――パリに秘密の恋など存在しない。観客たちは第14号ボックス席の兄弟に注目していた。良家の青年がオペラ歌手と結婚するなど前代未聞のことだったからだ。
舞台に現れたクリスティーヌの顔は真っ白で、怯えているように見えた。しかし歌い出すと、その声はまさに天使のようだった。ああ、なんという歌声だろう! その夜、パリの誰もがクリスティーヌ・ダーエに恋をした。
彼女が有名な恋のアリアを歌い始めたその時――。
突然、オペラ座のすべての明かりが消えた。場内は闇に包まれ、誰も身動きも言葉も発せなかった。ほんの一瞬の沈黙。だが次の瞬間、女性の悲鳴が響き渡り、灯りが再びともった。
……しかし、舞台にクリスティーヌの姿はなかった。舞台裏にも、地下にも、どこにもいない。誰一人、彼女を見つけられなかった。
オペラ座は大混乱に陥った。観客も関係者も右往左往し、叫び声と騒ぎが渦巻いた。支配人室にも人々が押し寄せ、警察が駆けつけて質問を浴びせたが、誰も答えられなかった。アルマン支配人は怒り、声を荒げた。
その時、ジリー夫人が娘メグを伴って現れた。
「出て行け、女!」アルマンは怒鳴った。
「モンシュー、いま行方不明なのは三人です!」ジリー夫人は毅然と言い放った。「さあ、メグ。支配人たちに話してごらん」

ジェニファー・バセットによる『オペラ座の怪人』
メグの顔は青ざめていた。彼女は小さな声で語り始めた。
「明かりが消えた時、私たちはちょうど舞台の裏にいました。あの悲鳴が聞こえました……おそらくクリスティーヌ・ダーエの声です。その後すぐに明かりは戻りました。でも、クリスティーヌの姿はどこにもなかったのです。私たちは恐ろしくなって、楽屋へ逃げようとしました。人々があちこちで走り回っていて……その時、シャニュ子爵を見かけました。彼は顔を真っ赤にして怒鳴っていました――【クリスティーヌはどこだ? クリスティーヌはどこだ?】と。その背後に突然ペルシャ人が現れ、子爵の腕を取りました。彼に何か囁きかけると、二人はクリスティーヌの楽屋へ入っていったのです」
「それで? その後は?」フィルマン支配人が食い入るように尋ねた。
「……誰も知りません」メグは唇を震わせた。「私たちが楽屋を覗いたとき、そこには……誰もいなかったのです!」
第8部:湖の上の家
灯りがついた瞬間、ラウルは駆け出した。階段を駆け下り、廊下を抜け、舞台裏へと走る。クリスティーヌの楽屋へ続く廊下で、突然誰かの手が彼の腕をつかんだ。
「どうしたのだ、若き友よ? どこへ走っている?」
黒い帽子の下からのぞく長い顔――それはペルシャ人だった。
「クリスティーヌだ!」ラウルは息を切らしながら叫んだ。「エリックが彼女を連れ去ったんだ! どうか助けてくれ。あの湖の上の家に行くにはどうすればいい?」
「ついて来い」ペルシャ人は低く言った。二人は急いでクリスティーヌの楽屋へ入った。ペルシャ人はドアを閉め、壁一面にある大きな鏡の前に立った。
「この部屋には扉は一つしかないはずだろう?」ラウルが言いかけると――
「待て」ペルシャ人は鏡に両手を当て、場所を変えながら押した。最初は何も起こらなかったが、やがて鏡がゆっくりと動き、黒い穴が口を開けた。
「早く! だが用心しろ。私はエリックを知っている。彼の秘密を理解しているのだ」

ジェニファー・バセットによる『オペラ座の怪人』
二人は地下深くへと降りていった。隠し扉を抜け、暗い階段を下り、迷路のような通路を進む。その間、ペルシャ人は常に耳を澄ませ、怪しい物音に注意を払っていた。
「湖を渡ってはいけない。エリックが見張っている。回り込んで、裏から忍び込む。秘密の入口を知っているのだ」
やがて目的の場所に着いた。暗闇の中、ペルシャ人は壁を探るように手で撫でた。
「……あった」彼が小声でつぶやくと、壁がわずかに動き、小さな扉が開いた。二人は静かに中へ入り、扉は音もなく閉じた。もはや外へは戻れない。
中は闇に包まれていた。二人は息を潜めて耳を澄ます。ペルシャ人が壁に手を触れた瞬間、顔色を失った。
「しまった……! 間違った扉だ。ここはエリックの拷問部屋、鏡の間だ! シャニュ子爵、我々はもう助からん……」
ラウルは意味を理解できなかった。だがすぐに悟ることとなる。灯りがぱっとともり、不気味な笑い声が響いた。エリックは彼らの存在を知っていたのだ。
部屋の壁も床も天井もすべて鏡で覆われていた。鏡には木々や花、川の映像が映り込み、それらがゆらめき、踊って見える。部屋は次第に熱気を帯び、灼けつくように暑くなった。
喉が渇く……水が欲しい。ラウルは目を閉じても、鏡の川が彼を嘲笑うように揺れ続ける。やがて体は重く、声も出せず、目すら開けられなくなった。渇きは消え、ただひどい疲労だけが全身を支配した。
「――クリスティーヌ、ごめん。君を助けたかったのに……僕はここで死んでしまうのか。」
その様子を、一枚の鏡越しにクリスティーヌが見つめていた。背後にはエリックが立ち、彼女の腕を押さえていた。
「見ろ、クリスティーヌ。彼は死にかけている。しっかり見るんだ。目を逸らすな!」
クリスティーヌは声も出せず、悲鳴をあげたいのに言葉が出なかった。しかし、やがて必死に声を絞り出した。
「どうしてそんなことができるの、エリック! 私を殺せばいいじゃない!」
「私は君を愛しているのだ、クリスティーヌ。私の妻になり、愛してくれるなら……ラウルもペルシャ人も助けてやろう」
クリスティーヌはゆっくりと振り返り、その恐ろしく醜い顔を見つめながら、かすかな声で言った。
「……ええ、エリック。今この瞬間から、私はあなたの妻です」
そう言うと、彼女は両腕を彼の首に回し、醜い口にそっと、しかし確かに愛情を込めて口づけした。そして腕を離し、静かに言葉を続けた。
「哀れな、悲しいエリック……」
エリックは呆然と見つめ、震える声でつぶやいた。
「……キスを、くれたのか。私が頼んだわけでもないのに……自ら……! ああ、クリスティーヌ、天使よ。生まれて初めての口づけだ。母でさえ、一度も私にしてくれなかった……。二つの歳で初めて仮面を与えられ、それからは顔を背けられ続けた……」
彼は顔を両手で覆い、声をあげて泣いた。やがてクリスティーヌの足元にひざまずき、嗚咽の合間に言った。
「君は自由だ、クリスティーヌ。ラウルと結婚し、幸せになれ……だが時々でいい、エリックのことを思い出してくれ。さあ、早く行け! ラウルとペルシャ人を連れて、逃げるんだ!」
第9部:ジリー夫人、ペルシャ人を訪ねる
あの恐ろしい夜から数週間後のある午後、ジリー夫人はリヴォリ庭園の近くにある一軒の家を訪ねた。階段を上がり、最上階の部屋の前で立ち止まると、ドアを開けたのはペルシャ人だった。
「どうぞ、お入りなさい」
彼は静かにそう言った。
二人は窓際の椅子に腰掛け、リヴォリ庭園を見下ろしながら話し始めた。
「ええ……」ペルシャ人はゆっくりと言った。「ファントムはもう死にました。生きることを望まなくなったのです。三日前、私は彼の亡骸を見ました。もう彼に殺される心配はありません」
「つまりファントムは、本当に人間だったのですか?」ジリー夫人が問いかける。
「ええ、彼の名はエリック。フランスに生まれましたが、私はペルシャで彼と出会いました。彼は有名な建築家で、私は一時期彼と共に働き、友人でもありました。パリへ来たとき、私は彼を追ってきたのです。エリックは非常に聡明で、同時に危険な男でした。二人、三人分の場所に同時に存在するように振る舞えたし、ここにいるのに声はあちらから聞こえる、といった芸当もできた。ロープや鏡、隠し扉を使ってあらゆる仕掛けを操れたのです。オペラ座の建設にも関わり、地下に秘密の通路や湖の上の隠れ家を作り上げたのも彼でした」
「しかし彼は、その恐ろしく醜い顔ゆえに、外の世界では生きられなかった……哀れなエリック。あれほどの才を持ちながら……同時にこれほど醜い顔を持った人間はいませんでした。人々は彼の顔を見ると悲鳴をあげ、彼を恐れた。だからこそ彼は【人間】でありながら【怪人】として生きざるを得なかったのです。けれど最後には、やはり人間だった……。彼もまた女の愛を求めていたのです」
ペルシャ人はそこで言葉を切った。ジリー夫人が静かに尋ねた。
「では、クリスティーヌ・ダーエとラウル子爵は……?」
ペルシャ人は微笑んで答えた。
「若きラウルと美しいクリスティーヌ……さて、二人に何が起きたのか。それは誰にも分かりません」
――物語 終わり――
コメント💬💬💬
『オペラ座の怪人』は、苦しみとどう向き合うかを示す物語の好例です。主要な登場人物――怪人エリック、クリスティーヌ・ダーエ、そしてラウル・ド・シャニュ子爵――はそれぞれ深い苦しみを抱え、その歩みは人が痛みの中に意味を見出す、あるいは見出せない様を浮き彫りにしています。
- 怪人の苦しみ
エリックの苦しみは、生まれつきの醜い顔と、それがもたらした孤独に根ざしていました。社会から、そして自らの母親からさえ拒絶され、彼は孤立と心の痛みに苛まれながら生きてきたのです。その孤独が彼の天才的な音楽性や建築の才能を生んだ一方で、同時に支配欲やクリスティーヌへの執着、暴力的な愛へとつながってしまいました。
苦しみを超えるどころか、それに囚われてしまった彼の愛の追求は、憎しみと絶望に歪められ、破滅の道へと導かれてしまったのです。
- クリスティーヌの苦しみ
クリスティーヌの苦しみは、より内面的で心理的なものでした。彼女はラウルへの愛と、怪人への恐怖と奇妙な魅了との狭間で引き裂かれます。その中で彼女が探し求めたのは、自らの声と、自分自身の生き方でした。
最終的に彼女は、慈悲という行為を通じて苦しみに意味を見出します。怪人に優しさを示した彼女の決断は、彼自身を救っただけでなく、自分自身の恐れや痛みをも乗り越えるものとなりました。
- ラウルの苦しみ
ラウルの苦しみは、より直接的で単純です。愛するクリスティーヌを失う恐怖と悲しみの中にありました。心理的な歪みではなく、純粋で無私の愛が彼を突き動かし、命の危険を顧みずに怪人に立ち向かわせました。ラウルの忠実さと勇気は、愛する人を守るために痛みを引き受ける姿を体現しています。
こうして、怪人のように苦しみに飲み込まれて破滅する者もいれば、クリスティーヌやラウルのように、それを成長や慈悲、勇気の契機とする者もいます。
人間は誰しも苦しみに直面します。そのとき私たちは、暗闇に沈むか、あるいはそこから意味と救いへの道を見出すか――その選択を迫られているのです。
もし私が怪物だというのなら、それは人々の憎しみが私をそうしたのだ。だが、もし私が救われるとしたら、それはあなたの愛が私を贖うからだ。

ジェニファー・バセットによる『オペラ座の怪人』
画像クレジット:Pinterest
他の項目:
- 『カモメに飛ぶことを教えた猫』違いを越えて生まれる愛
- 『三つの願いの物語』人生の選択にまつわるフィクション
- 人生の意味|なぜ生きるのか?|後悔しない生き方を送るために大切なこと
一緒に学びませんか?